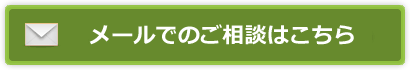ライバルが注目しない分野・市場に参入 ニッチ戦略でミニリーダーを目指そう
Question→弊社も将来に向け、新規事業の⽴ち上げを考えています。しかし新規事業はリスクもあるので、できるだけ競合の少ないニッチな市場への進出を検討しているのですが、最近「ブルーオーシャン戦略」という⾔葉もよく⽿にします。ニッチ戦略とブルーオーシャン戦略はどのように違うのでしょうか。
Answer→どちらも競合を避けるという意味では、よく似た⾔葉といえます。ただ、ニッチ戦略が「既存の市場のなかで、誰も⼿をつけていないすき間市場を狙う戦略」であるのに対し、ブルーオーシャン戦略は「既存の市場とは異なる、競合のいない新たな市場を創造することで、競争を避ける戦略」と解されます。
すき間を攻めることがニッチ戦略やり⽅次第でその分野の先駆者に
ニッチ戦略とは、「すき間」市場を狙うというビジネス上のフレームワークです。ニッチには「すき間」の意味があり、「⼤⼿が狙わない」「⼤⼿が狙えない」「⼩規模ゆえ⾒逃されやすい」市場にあえて焦点をあて、そこに進出することでリーダー的な存在(ミニリーダー)を確⽴します。⼤企業相⼿に資本⼒や経営資源では勝てなくても、⼩さい市場を攻めることで活路を⾒出せる可能性が広がります。これがニッチ戦略です。
ニッチ戦略に類似した⾔葉に「ブルーオーシャン戦略」があります。ブルーオーシャン戦略は「競争回避戦略」ともいい、競争が激化している「レッドオーシャン」市場で勝負せず、競争がない、あるいは少ない市場を新たに創出することを主眼に置いた戦略です。競争相⼿のいない市場に進出する点で両者は似ていますが、ブルーオーシャン戦略は市場環境にも影響されるため、必ずしもうまくいくとは限らないのが特徴です。
ニッチ戦略が有効といわれる要素としては、「特定の層に⾃社製品やサービスを深く理解してもらいやすい」「競争のない市場に進出できる」「ブランドの独⾃性を強化できる」「ターゲットを絞れるため、効率よく経営資源が活⽤できる」点があげられます。
ニッチ戦略はデメリットもあるが⾃社の成⻑を模索するために有効
ニッチ戦略のメリットとしては、競争が少ないこと、顧客ロイヤルティーを構築しやすいこと、⽐較的早期に効果が得られやすいことなどがあげられます。⼀⽅でデメリットとしては、市場規模が限定されてしまうこと、需要の変動次第で厳しい局⾯に⽴たされる可能性があること、顧客基盤が限定されるため顧客が離れたときのダメージが⼤きいことなどがあります。また、ひとたびニッチ戦略に成功すると、その市場がたちまち「レッドオーシャン化」してしまう可能性もあります。
このようにニッチ戦略は中⼩企業が先駆者として確⽴する戦略として有効ですが、メリットが多い反⾯デメリットもあります。では、ニッチ戦略を推進するにはどのようなことに留意すべきでしょうか。まず、焦らず、⻑期的な視点で考えることが重要です。また、迅速さや効率性を重視し過ぎるあまり、綿密な計画を⽴てずに進出してしまうと法的トラブルになりかねないため注意が必要です。さらに、経営資源が限られているため、最適な配分を徹底することも⼤切です。
ビジネスの可能性を模索するためにも、⾃社の商品・サービスを分析し、ニッチ市場に参⼊できる⾒込みがありそうならば、戦略的なアプローチの⼀つとして検討してみてはいかがでしょう。

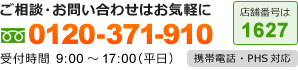

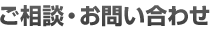
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)