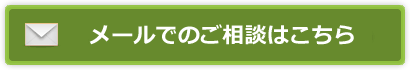役員報酬はどう決める? 税務と経営の両面から考えるポイント
中小企業の経営者にとって、役員報酬の設定は重要です。適切な報酬設定は会社と個人にメリットをもたらす一方、不適切な報酬設定は税務調査のリスクや資金繰りの悪化を招く可能性があります。今回は、役員報酬決定の基本から実務的な設計手法までを解説します。
役員報酬の基本の「キ」と損をしないための決め方の鉄則
役員報酬は、取締役や監査役に支払われる報酬で、一般従業員の給与とは税務上のルールが異なります。中小企業では経営者が株主兼役員のケー
スが多く、役員報酬は会社の利益配分方法の一つとして重要な意味を持ちます。適切に設定すれば役員報酬は損金(経費)として認められ節税につ
ながりますが、ルールに反すると、税務署から否認されるリスクもあります。税法上、役員報酬は主に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」と「業績連動給与」の3種類に分類されます。なかでも中小企業で一般的なのは「定期同額給与」です。毎月同額の報酬を支給し、年度途中での報酬額の増減は原則認められておらず、年度途中で変更した場合、変更後の金額は損金に算入されない可能性があります。報酬額の通常改定は、事業年度開始日から3カ月以内にする必要があります。「事前確定届出給与」は賞与などの変動報酬を支給する場合に用います。支給額や時期を事前に定め、原則、株主総会などの決議の日から1カ月以内か会計期間開始の日から4カ月以内のいずれか早い日に税務署へ届け出る必要があります。届出通りに支給することで損金算入が認められます。「業績連動給与」は、有価証券報告書にて開示する必要があるなどの要件があるため、上場企業や大企業が対象になります。役員報酬を決める際のポイントとして「過大報酬」の問題があります。会社の規模や業績、同業他社の水準から見て著しく高額な報酬は「不相当に高額な部分」として損金に算入されない可能性があり、過大報酬に該当するかは、業績や職務内容、同業他社との比較で総合的に判断されます。
資金繰りも考慮しよう 報酬シミュレーションを解説!
役員報酬の設定にあたっては正しい手続きを踏むことも重要です。株主総会で総額を決議し、取締役会で各役員への配分を決定します。特に議事録の作成・保管は、税務調査で報酬根拠を示すために不可欠です。また、役員報酬の設定は、節税効果だけでなく会社の資金繰りにも大きな影響を与えます。特に中小企業では、資金繰りの観点からの検討が不可欠です。報酬が高すぎると運転資金不足や設備投資資金の確保が困難になり、低すぎると法人税負担が増加します。また、報酬額は社会保険料負担にも影響するため、総合的に検討する必要があります。たとえば、業績が右肩上がりのA社では、節税目的で役員報酬を月額100万円に設定しました。結果として税負担は月額50万円のときよりも軽減されましたが、毎月の支出が増えたために資金繰りが逼迫し、急な運転資金の確保に支障をきたしました。一方、堅実経営を続けるB社では、役員報酬を月額30万円に抑えることで、内部留保
を厚くしながら設備更新や将来の事業展開に備えています。資金面での余裕が経営の安定にもつながっています。このように、役員報酬の設定は税務と経営の両面から考えるべき重要な意思決定です。実務的なポイントとしては、①適正な報酬水準の見極め、②税金とのバランス、③資金繰りへの配慮、④将来の事業計画との整合、⑤定期的な見直しの5点があげられます。最適な報酬は会社の状況により異なるため、業績、資金需要、将来計画を総合的に考慮し、専門家と相談しながらの設計をおすすめします。

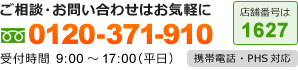

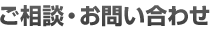
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)