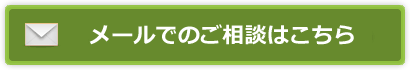企業の事業承継は改善傾向だが不安感も 事業承継の実態と留意点の理解が重要に
帝国データバンクがまとめた『全国「後継者不在率」動向調査』によると、国内企業の後継者不在率は過去最低となり、中⼩企業の事業承継の実態に変化が出てきました。しかし、今なお続く後継者不在問題に対し、企業はどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
後継者不在率は改善傾向となるも 後継者難倒産も多く予断を許さず
⽇本の多くの中⼩企業は、⻑きにわたり後継者問題に悩まされています。特に承継の時期やタイミングなどをどうするべきかについては、経営者にとって喫緊の問題であるといってよいでしょう。では、国内企業の後継者不在率がどのようになっているのかを⾒ていきましょう。帝国データバンクの調査では、2024年の後継者不在率は52.1%となり、過去最⾼であった2017年(66.5%)と⽐較すると14.4ポイント低下しました。これは調査開始以降で最低値となっています。国や⾃治体、地域⾦融機関などの後押しもあり、⽇本企業の後継者不⾜は改善の兆しが⾒える⼀⽅で、前年からの改善幅は⼩さく、改善のペースは鈍化傾向であるとみられています。後継者不在率を年代別で⾒ていくと、「50代・60代」で後継者不在率が悪化し「80代以上」は全年代で最低となっています。そして業種別の後継者不在率は、調査開始以降初めて全業種で60%を下回る結果となりました。このように、⽇本企業の後継者不在率は改善傾向が⾒受けられる反⾯、後継者不在による倒産が相変わらず多いことは⾒過ごせません。2024年の「後継者難倒産」は507件で、前年よりも減少したものの2年連続で500件を上回り、過去2番⽬の⾼⽔準となりました。「経営者の病気、死亡」で倒産した例は316件と初めて300件を超え、全倒産に占める割合も年々増加しています。団塊の世代が75歳以上の後期⾼齢者となる「2025年問題」が遂に到来し、ピッチを上げて後継者不⾜を解決していくべきフェーズに⼊ったといっても過⾔ではないでしょう。
事前準備と事業承継の傾向を掴み 企業の技術やノウハウを引き継ぐ
事業承継の形態には「親族内承継」「企業内承継」があり、最近ではM&Aも多くみられます。また、親族内承継にこだわらない「脱ファミリー
化」が加速しており、同族承継以外の「内部昇格」「M&A」「外部招聘」の割合が増加しています。そして、承継対象者も業界経験が「10年以上」ある後任代表者が8割超であり、ベテラン志向になっているようです。企業が事業を承継するうえで重要なのは「事業承継により何が引き継がれるのか」を理解することです。事業承継により「⼈」「有形固定資産」「無形固定資産」が引き継がれます。この重要な経営資源を最適に次世代へ引き継げれば、事業を承継した後も⾃社の伝統を維持しつつ成⻑することが期待できます。中⼩企業が事業承継を成功させるには、まず、早期の計画や準備が重要です。経営者がまだ健康なうちに後継者の選定と育成を始め、段階的に業務を引き継ぐことで、混乱を避けスムーズな承継が進められます。次に、財務・法務を整備し、株式の譲渡や移転、契約書の再締結、労務管理の確認などを通じて、法的トラブルを未然に防ぎましょう。また、従業員や取引先、株主、相続⼈など、関係者の理解を得ておくことも⼤切です。事業承継はセンシティブな話ですが、決して避けては通れません。⾃社が⻑く培った技術やノウハウがどこにも引き継がれずに、後継者不在によって途絶えてしまうのは実に惜しいことです。もし、まだ後継者について決まっていないようであれば、今から「誰に」「いつ」「どのように」事業を承継するか準備しておくとよいでしょう。

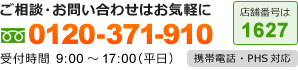
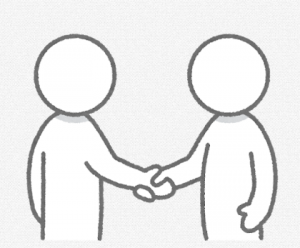
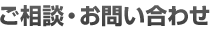
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)