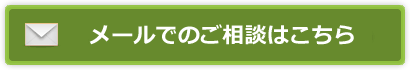資本金1億円以下でも対象に? 「外形標準課税」適用の新たな盲点
外形標準課税は「資本金1億円超の大企業だけが対象」と誤解されがちですが、令和6年度税制改正により、資本金が1億円以下でも適用となるケースが生じます。また、M&Aや増資を契機に対象となる場合もあります。今回は見落としがちな適用要件と対策を解説します。
「外形標準課税」とは その背景と制度の構造
外形標準課税とは、法人事業税の計算方法の一つで、従来の所得のみに課税する方式に加え、付加価値額や資本金などを課税標準とする制度です。企業の外形的な事業規模に応じて税負担を求め、税収の安定化や税負担の公平化が目的です。本制度では赤字企業でも一定の税負担が発生するため、財務計画に与える影響は大きく、経営戦略上も重要な制度でしょう。一般的には「資本金1億円超」の法人が対象とされていますが、令和6年度税制改正により、適用範囲が見直されました。
資本金が1億円を超えている法人はこれまで通り対象となりますが、今回の改正で資本金1億円以下でも「前事業年度が外形標準課税の対象法人であり、かつ、事業年度末日の資本金の額が1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える」場合、外形標準課税の対象となりました。これは、2025年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。なお、改正内容には公布日以後に減資をする場合の措置も講じられているため適用要件の確認が必要です。さらに、中小企業が大企業の100%子会社となった場合にも注意が必要です。資本金1億円以下であっても、特定法人※の100%子法人などであり、かつ、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人は外形標準課税の対象となり、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。本改正で新たに対象となる子法人は法人事業税の計算において一定額が軽減される経過措置が設けられています。
※ 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人(非課税法人や所得割のみで課税される法人などを除く)、または相互会社(外国相互会社を含む)
よくあるケーススタディと経営判断への影響
実務上よく見られるケースをもとに、外形標準課税の適用リスクを整理します。
ケース1:資本政策への影響
ある企業が事業拡大のために増資を行い、資本金が1億円を超えたとします。その後、財務体質の改善を目的に減資を実施して資本金を1億円未満に戻した場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には、引き続き外形標準課税の適用対象となります。これは、形式的な課税逃れを防ぐための措置であり、経営者の想定を超えて中長期的な税負担が残る可能性があります。資本政策を検討する際には、この点も十分考慮する必要があります。
ケース2:M&Aによる影響
中小企業が大企業に買収され、100%子会社となった場合、単体では資本金1億円以下でも、親会社を含めた企業グループ全体で資本金と資本剰余金の合計が一定基準を超えると、対象法人となる可能性があります。この場合、買収された側のみならず、買収する企業側にとっても、想定外の税負担増加となるリスクがあります。
外形標準課税は、見落とされがちな経営リスクですが、一度適用されると税負担が大幅に増える可能性があります。資本政策やM&A戦略の立案時に、外形標準課税の影響を十分に検討しておくことが不可欠です。また、制度改正の動向を継続的に注視し、専門家と連携することも重要です。
経営判断にあたっては、単に資本金額だけを見るのではなく、制度の改正動向や企業グループ全体の構造、将来的な資本取引の影響などを含めた総合的な視点から判断するようにしましょう。

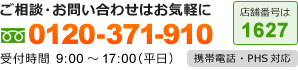

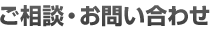
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)