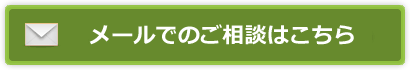雇用調整助成金終了後の課題 人件費マネジメントの見直し
コロナ禍で活用されてきた「雇用調整助成金」の特例措置が2023年3月31日で終了し、受給した多くの企業が人件費マネジメントの見直しを迫られています。今回は、受給終了後に企業が抱える雇用リスクと、賃金制度や制度設計の工夫について考察します。
雇用調整助成金の特例措置が終了 ほかに活用できる助成金は?
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、休業や出向などの雇用調整を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。コロナ禍においては、雇用調整助成金について大規模な特例措置がとられ、受給要件の緩和や助成額の日額上限と助成率の引上げが行われました。
この特例措置は、2020年4月1日から2022年11月30日までの期間が対象で、この特例を利用した事業主については、2022年12月1日から2023年3月31日までの期間において一定の経過措置が設けられました。こうした措置の結果、2020年4月から2023年3月末までの累積で、雇用調整助成金の支給決定件数は約631万件、支給決定額は約6兆円となっています。
雇用調整助成金を受給した企業の多くでは、受給直後は失業の発生を回避でき雇用を維持することができましたが、受給終了直後には離職が集中し雇用が減少しました。その後も、採用率は低く離職率が高い状況にあり、雇用は回復しきれていません。また、従業員のモチベーションや生産性の低下も課題となっています。
そこのフォローのために利用できる助成金に、生産性向上のための設備投資と共に事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合の「業務改善助成金」や、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取り組みを実施した場合の「キャリアアップ助成金」などがあります。賃金アップなどを伴いますが、一定額が助成されるため少ない負担で従業員のモチベーション維持が期待できます。
企業の持続と成長のためには人件費の削減ではなく最適化を
助成金の活用のほかに、人件費に対する見直しを行うのも一つの方法です。
人件費は、給与や賞与、退職金、福利厚生費など、企業経営においては大きなコストであると同時に、従業員のモチベーションを大きく左右する要因でもあります。そこで、人件費の削減ではなく最適化によって、企業の生産性と従業員の満足度を向上させることが重要となります。
人件費の最適化には、業務プロセスの見直しや、柔軟な労働時間制度の導入、成果に連動した賃金制度の整備、費用対効果を考慮した福利厚生制度の運営などが有効な手段となります。具体的には、業務の標準化によって人材を再配置するフレックスタイム制を適用し、時間外労働の抑制と効率化に取り組んでいる事例などがあります。こうした検討を行う際は、人件費の構成をさまざまな切り口で「見える化」するとよいでしょう。
雇用調整助成金以外にも助成金はありますが、用途が異なるため自社にとって有効か判断することが大切です。また、助成金活用以外の対策として、人件費の最適化も検討するとよいでしょう。制度を見直すことで、持続可能な人件費マネジメントを実現していきましょう。

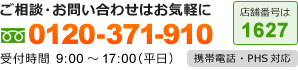

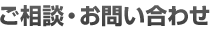
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)