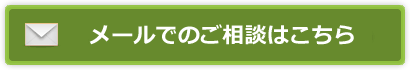2026年度から未管理の著作物も利用可能に 新設の『未管理著作物裁定制度』とは?
世の中に公表されているものの、利用の可否について著作権者の意思を確認できない著作物が増えています。こうした著作物を利用できるようにする「未管理著作物裁定制度」が2026年度より始まります。制度が生まれた背景や利用の際の流れなどを確認しましょう。
著作権者の意思が確認できない際申請を受けた文化庁が裁定を行う
通常、第三者の著作物を使用する場合は、その著作権者に許諾を得る必要があります。もし、無断で使用すると著作権法違反となり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。しかし、近年は利用の可否について、著作権者の意思を確認できないことも少なくありません。インターネット上に公開されている著作物に、利用のためのルールや著作者への連絡先などが記載されていないケースなどです。こうしたケースに対応するため、2023年5月に「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、「未管理著作物裁定制度」という制度が創設されました。この制度により、利用ルールや問い合わせ先、著作権者の連絡先などがわからない著作物でも、一定の手続きを踏むことで利用可能になる場合があります。
これまでも、著作権者が不明だったり、連絡が取れなかったりする場合に、文化庁へ申請することで、著作物を第三者が利用できる裁定制度は存在していました。しかし、従来の制度では、著作権者の連絡先が判明していても、利用の申し入れに対する返答がない場合には対応していませんでした。そこで、新しい未管理著作物裁定制度では、対象をより広く「著作権者の意思が確認できなかった場合」と定めました。利用ルールや問い合わせ先、連絡先などが明示されていない場合のほか、著作権者の連絡先に利用の可否を問い合わせて14日以内に応答がなかった場合も「著作権者の意思が確認できなかった」とみなされます。一方、サイト上に「無断転載禁止」などの利用ルールが明示されていたり、14日以内に応答があったりした場合は、制度を利用できません。
利用希望者は補償金を支払い著作権者には利用料が支払われる
未管理著作物裁定制度を使って管理されていない著作物を利用するには、利用希望者が著作権者の連絡先や利用ルールなどを調べる必要があります。調べてもこれらが見つからない、または著作権者に連絡しても14日以内に返答がない場合は、文化庁に裁定を申請します。審査が通れば裁定され、利用希望者は補償金を指定補償金管理機関に支払うことで、希望の著作物を使用できるようになります。ここでいう裁定とは、文化庁長官が著作物の利用を認める決定を下すことを意味します。
注意したいのは裁定を受けたからといって、著作権が自分のものになったり、著作物を制限なく自由に使い続けたりできるわけではありません。たとえば、裁定実績と著作物に関する情報は文化庁により公開されるので、後から利用されていることを知った著作権者が文化庁に請求すれば、その著作物は裁定を受けた第三者でも利用できなくなります。また、著作権者は後からでも、著作物の利用料(ライセンス料)を受け取れます。この利用料は指定補償金管理機関から支払われます。
もちろん、利用希望者と著作権者が利用条件や利用料などをあらためて協議したうえで、利用を継続させる道も残されています。未管理著作物裁定制度の目的は、著作権者自身も気づいていなかった利用ニーズのある著作物の活用を促すことにあります。制度が創設されることにより、事業者においては法的なリスクを回避しながら、未管理の著作物を事業に利用できるようになります。自社コンテンツへの活用や新たなビジネスモデルの創出など、さまざまな可能性が広がる同制度について、理解を深めていきましょう。

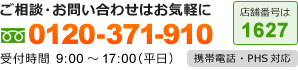
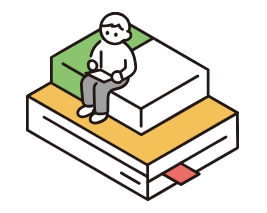
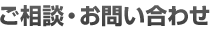
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)