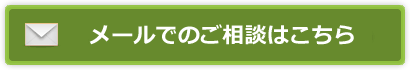カスハラか正当な要求か判断するには? 線引きの基準と悪質な場合の法的な対応
企業として、正当なクレームには真摯に対応する必要があります。⼀⽅で、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」に対しては、従業員を守るためにも毅然とした態度で臨まなければいけません。正当なクレームとカスハラの違いを理解し、対応策を準備しておきましょう。
カスハラ顧客の⾔動に⽋けている社会通念上の妥当性と相当性
顧客からのクレームは企業にとって、製品やサービスの改善や顧客満⾜度の向上につながる貴重な機会となりますが、その正当性は⼗分に精査しなければいけません。なぜなら、度を超えた悪質なクレームは、カスハラに該当する可能性があるためです。正当なクレームとカスハラの明確な区別が、従業員を守るうえで極めて重要です。正当なクレームとは、商品やサービスに対する具体的な不満や改善点を、常識的な範囲と⽅法で伝えることを指します。たとえば「購⼊した商品が初期不良だった」「サービスの質が契約内容と異なる」といった、事実に基づいた指摘などです。企業の迅速かつ誠実な対応により、顧客との信頼関係の回復や業務改善などにつながります。⼀⽅、カスハラは「要求の妥当性」と「⾔動に対する社会通念上の相当性」の⽚⽅もしくは両⽅を⽋くものを指します。たとえば、企業の提供した商品やサービスに、明らかに瑕疵・過失がないにもかかわらず「交換しろ」「返⾦しろ」などと、クレームをつけるのは、要求に妥当性がないカスハラといえます。また、顧客側が暴⾏、脅迫、中傷、暴⾔、威圧、⼟下座の要求、継続的な⾔動、拘束的な⾔動、差別的な⾔動、性的な⾔動、従業員への個⼈攻撃といった⼿段で⾃⾝の要求を実現しようとしてきた場合は、妥当性のあるなしを問わず、社会通念上不相当なカスハラとなります。ただし、企業の提供したサービスに過失があるなど、要求に妥当性がある場合、顧客からの商品交換や⾦銭補償、謝罪(⼟下座など過剰なものを除く)の要求は、社会通念上の相当性があると判断され、カスハラに該当しないこともあります。
従業員をカスハラから守るために法的責任を問うことも検討
カスハラが起きた場合、企業は従業員を守るためにも、法的な対応を検討する必要があります。たとえば、カスハラによって従業員が精神的な苦痛を受け、うつ病などの精神疾患を発症した場合、カスハラ⾏為を⾏なった顧客は、⺠法の不法⾏為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。企業側は、被害を受けた従業員をサポートするようにし、こういった場合にも早い段階で専⾨家に相談することが⼤切です。また、顧客の⾏為が、企業や従業員の正常な業務を妨害するものであれば、刑法上の業務妨害罪に該当する可能性があります。たとえば、店舗内で⻑時間にわたり⼤声で罵倒し、ほかの顧客の利⽤を妨げたり、電話やメールで執拗に連絡を繰り返して業務に⽀障をきたしたりする⾏為などがこれに当たります。特に、威⼒を⽤いて業務を妨害した場合は威⼒業務妨害罪、虚偽の情報を流布して業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪が成⽴する可能性があります。警察に被害届を提出し、状況によっては刑事告訴を⾏うことで、加害者に法的責任を問うことができます。さらに、公衆の⾯前で侮辱的な発⾔を繰り返す場合は、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があり、不退去罪や建造物侵⼊罪の適⽤も考えられます。これらの法的措置を検討する際には、⾳声や映像記録、メール履歴、⽬撃者の証⾔など、客観的な証拠の存在が重要です。証拠がなければ、法的な主張が認められない可能性が⾼まります。そのためカスハラの疑いがある状況では、可能な限り記録や証拠を残すよう徹底しましょう。

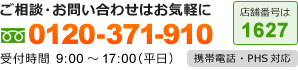

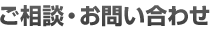
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)