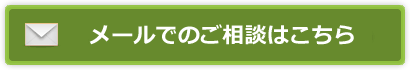紙かデータか? いつまで保管? 領収書・請求書の保存ルール
日々の事業活動で発生する領収書や請求書は、税務申告の根拠となる重要な証憑書類です。しかし、保存期間や方法を誤ると、税務調査での指摘対象になることもあります。今回は、紙と電子データそれぞれの保存ルールと実務上の注意点について解説します。
領収書の保存は何年必要? 基本ルールと実務ポイント
まず領収書の保存期間について確認しましょう。法人は原則7年間、青色申告書提出の個人事業主も同じく7年間の保存が必要です。白色申告の個人事業主は5年間です。また、法人が欠損金の繰越控除の適用を受ける場合は、帳簿書類の保存期間が10年に延長されます。これは繰越控除期間が延長されたことに伴い、関連書類の保存期間も延長されたためです。
保存対象となる書類は、領収書だけではありません。請求書、契約書、納品書、見積書、注文書なども含まれます。また、消費税の仕入税額控除を受けるための書類や、電子帳簿保存法の関係書類も別途管理が必要な場合があります。特に2023年10月開始のインボイス制度導入後は、適格請求書の要件を満たす書類の保存が重要です。
保存方法については、従来は紙での保存が基本でしたが、現在はスキャンやPDF保存でも可能となりました。2022年1月施行の電子帳簿保存法改正により、スキャナ保存の要件が大幅に緩和され、スマートフォンでの撮影も認められるようになりました。スキャナ保存を行なった場合、一定の要件を満たせば原本の即時破棄も可能です。感熱紙のレシートなどは時間の経過で文字が消えやすいため、早期の電子化を推奨します。
実務では、保存形式よりも「いつ・誰が・なぜ」必要になるかを意識した管理が大切です。税務調査の際に迅速に書類を提示できるよう、日付・取引先・金額での検索機能を確保し、整理された状態で保管することが重要です。保存期間の起算点は、法人の場合は各事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からとなります。
電子化する際の注意点 電子帳簿保存法との関係は?
帳簿書類等を電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たすことが前提です。2024年1月からは、電子取引に係るデータ保存が完全義務化され、電子的に受け取った領収書や請求書は電子のまま保存しなければなりません。紙に印刷して保管しても、電子帳簿保存法上の適正な保管とはみなされない点に注意が必要です。
電子保存には、改ざん防止のためのタイムスタンプ付与や事務処理規程の整備なども必要です。タイムスタンプは受領後速やかに付与するか、または訂正・削除の履歴が残るシステムを使用することで要件を満たせます。事務処理規程については、国税庁のサンプルなどを参考にして、自社の実情に合わせて作成しましょう。
電子帳簿保存法による電子取引の要件は複数ありますが、主要なものは真実性の確保(タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の確保)と可視性の確保(日付・取引先・金額での検索機能の整備)です。これらをすべて満たす必要があります。
ただし、保存要件に対応できない相当の理由がある場合に限り、税務署長の判断で猶予措置が適用されます。猶予措置では電子データが存在することが必須で、紙保存のみは不可となります。また、税務調査時にはデータのダウンロードや書面提示に応じられる必要があります。
請求書や領収書の保存は、税務調査の際にも重要なチェック項目です。紙でも電子でも「要件を満たして正しく保管」することが大前提となります。事業の成長と共に増える証憑の管理を、しっかりと整備しておくことが、リスク回避と業務効率化につながります。

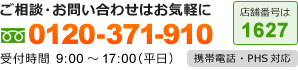
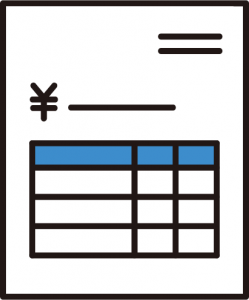
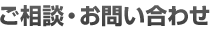
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)