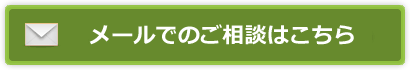事実無根の『風評被害』を受けたら!? 法的な枠組みと現実的な対応策
SNSへの悪意のある書き込みや、事実と異なる情報が拡散され、会社の名誉や信⽤が著しく損なわれるケースが後を絶ちません。こうした⾵評被害はさまざまな形で会社に損害を与えます。今回は、⾵評被害によるダメージを最⼩限に抑えるための対応策を解説します。
会社として正確な情報を発信して⾵評被害による不信感を払拭する
⾵評被害とは事実無根の噂や情報が広まることで、企業や商品、サービスなどの評価が下がり、損害をこうむることを指します。近年はインターネットやSNSの普及により、情報拡散のスピードが格段に向上し、企業における⾵評被害のリスクが増⼤しました。もし⾵評被害に遭った場合、企業は売上の減少だけではなく、顧客離れや株価の下落、従業員のモチベーションの低下、採⽤活動への悪影響など、さまざまなダメージを受け、場合によっては経営危機に陥るかもしれません。
⼀度損なわれた企業イメージや信頼は回復に時間がかかります。企業としては、順を追って適切に対処することが重要です。まずは⾵評被害の原因となった情報を特定し、事実関係を明確にしましょう。原因がデマや事実無根の情報に基づくものであれば、⾵評被害を打ち消すよう、正確な情報を発信しなければいけません。ホームページなどでの情報発信に加え、記者会⾒を開催し、企業の⽴場や⾒解を説明する場合もあります。2017年には医薬品原料メーカーの不祥事によって、無関係である同名の競泳⽤⽔着などを取り扱うメーカーに苦情が寄せられ、社⻑が「まったく関係のない会社」であることを説明するための緊急記者会⾒を開いたこともありました。また、SNSの運営会社に削除依頼をしたり、⾃社アカウントで⾵評被害に反論したりするなどの対応も効果的です。
こうした記者会⾒や情報発信などによって事態が収束すれば、それ以上のダメージを防げます。しかし、適切な対応を⾏なっているにもかかわらず、⾵評被害が収まらない場合は、法的な対応策も並⾏して検討していくことになります。
悪意のある投稿やデマについては情報の発信者に法的な責任を問う
SNS上の⾃社に対する悪意のある投稿によって⾵評被害が起きた場合には、情報の発信者に法的な責任を問うことができます。発信者が企業の社会的評価を低下させるような情報を⼝コミサイトやSNSなどの公然性の⾼い場所に投稿していた場合、名誉毀損罪が成⽴する可能性があります。名誉毀損罪は発信した情報が真実か虚偽かを問わず、また実際に社会的評価が低下していなくても、社会的評価を低下させる危険性のあるものと評価されれば責任を追及される可能性があります。そのため、真実でなくとも、それなりの事実を指摘して「腐った⾷材を使っている」「不祥事を隠蔽している」「不当に代⾦を取る詐欺企業」などのコメントは名誉毀損罪に該当する可能性が⾼いといえます。
また、虚偽の情報を流布し、企業の信⽤を毀損した場合には、信⽤毀損罪が成⽴する可能性があります。「経営破綻⼨前らしい」「幹部が資⾦を横領している」「商品がリコールされる」などのデマが信⽤毀損罪に該当します。信⽤毀損罪は名誉毀損罪のような公然性が問われないため、取引先や顧客との1対1のやり取りや、同僚グループ内での噂話などでも成⽴するので、従業員にも注意を促しましょう。噂話が事実の場合は、名誉毀損罪が成⽴する可能性があります。
ほかにも、企業の業務を妨害する⽬的で虚偽の情報を流布した場合には業務妨害罪が成⽴する可能性があります。こうしたデマや悪意のある投稿によって⾵評被害に遭った場合は、不法⾏為に基づく損害賠償請求を⾏うこともできるので、まずは、弁護⼠に相談することをおすすめします。

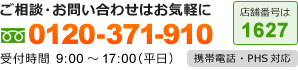

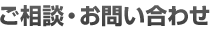
![0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)](http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/wp-content/themes/qtax_12e3/common/imgs/unit-contact.gif)